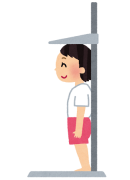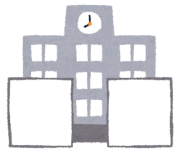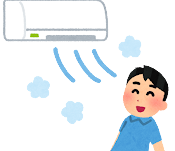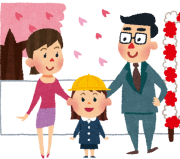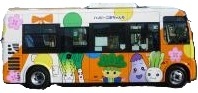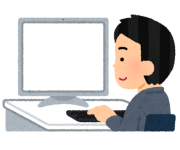要介護認定の審査迅速化への本市の取り組みについて
2025年6月議会
提言)
介護保険法では、「市区町村は申請を受けてから原則30日以内に認定を行わなければならない」と規定しているものの、多くの自治体でこの期間内に認定がされておらず、厚生労働省では事態の改善に向けた取り組みを進めています。そこで、本市としての取り組みについてお聞かせください?
提言)
介護保険法では、「市区町村は申請を受けてから原則30日以内に認定を行わなければならない」と規定しているものの、多くの自治体でこの期間内に認定がされておらず、厚生労働省では事態の改善に向けた取り組みを進めています。そこで、本市としての取り組みについてお聞かせください?
回答)
本市の取り組みといたしましては、要介護等認定調査員の人員の確保のほか、委託による認定調査の実施により、認定調査可能件数を確保するよう努めております。 また、主治医意見書の入手につきましては、医療機関と市の間で作成目安を設定しており、主治医意見書の提出が遅れている場合には、医療機関への連絡などを行っております。
今後、高齢者の増加とともに要介護等の申請者も増加することが予想されますことから、引き続き迅速化に努めるとともに、さらなる迅速化が図れるよう、介護認定審査会の年間回数や1回当たりの審査件数を増やすなどの検討もしていく必要があるものと考えております。
本市の取り組みといたしましては、要介護等認定調査員の人員の確保のほか、委託による認定調査の実施により、認定調査可能件数を確保するよう努めております。 また、主治医意見書の入手につきましては、医療機関と市の間で作成目安を設定しており、主治医意見書の提出が遅れている場合には、医療機関への連絡などを行っております。
今後、高齢者の増加とともに要介護等の申請者も増加することが予想されますことから、引き続き迅速化に努めるとともに、さらなる迅速化が図れるよう、介護認定審査会の年間回数や1回当たりの審査件数を増やすなどの検討もしていく必要があるものと考えております。
病児保育対象児童の小学6年生までの引き上げについて
2025年6月議会
提言)
国の「病児保育事業実施要綱」では、対象児童の上限を小学校に就学している児童、つまり6年生までとしています。また、病児病後児保育施設等を利用したい、或いは、利用せざる得ない親御さんにとって、対象年齢を小学6年生まで引き上げることは、利用できる機会が増えて利便性が向上し、子育て支援策の拡充にもつながり、意義があると考えますが、「こどもまんなか応援サポーター」である本市としての考えをお聞かせください?
回答)
病児保育対象児童の小学6年生までの引き上げにつきましては、現時点では実施の予定はございませんが、近年、共働き家庭が多く、急に仕事を休むことができないなどの理由から病児保育の利用の要望が高まる可能性も想定されますことから、需要変化に注視し、調査、研究してまいりたいと考えております。
国の「病児保育事業実施要綱」では、対象児童の上限を小学校に就学している児童、つまり6年生までとしています。また、病児病後児保育施設等を利用したい、或いは、利用せざる得ない親御さんにとって、対象年齢を小学6年生まで引き上げることは、利用できる機会が増えて利便性が向上し、子育て支援策の拡充にもつながり、意義があると考えますが、「こどもまんなか応援サポーター」である本市としての考えをお聞かせください?
回答)
病児保育対象児童の小学6年生までの引き上げにつきましては、現時点では実施の予定はございませんが、近年、共働き家庭が多く、急に仕事を休むことができないなどの理由から病児保育の利用の要望が高まる可能性も想定されますことから、需要変化に注視し、調査、研究してまいりたいと考えております。
障がい児用抱っこ紐の障害者(児)日常生活用具給付について
2025年6月議会
今後、当事者の意見やニーズの把握に努め、要件に該当するかを確認し、適宜、検討・見直しを図ってまいります。
提言)
障害があって座位の維持が困難なお子さんなどが外出する際には、福祉用バギーを利用することが多いですが、段差・階段・狭い歩道等では利用が難しいことがあります。また、通常の抱っこ紐を利用していても、成長して身体が大きくなるとサイズアウトしてしたり、首の支えが不十分であったり、低緊張児は沈み込み呼吸困難のリスクが発生します。そこで、各児童の特性に合わせて作られるのが障がい児用抱っこ紐です。障がい児用抱っこ紐の給付申請があった場合には、ぜひ前向きに検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか?
回答)障害があって座位の維持が困難なお子さんなどが外出する際には、福祉用バギーを利用することが多いですが、段差・階段・狭い歩道等では利用が難しいことがあります。また、通常の抱っこ紐を利用していても、成長して身体が大きくなるとサイズアウトしてしたり、首の支えが不十分であったり、低緊張児は沈み込み呼吸困難のリスクが発生します。そこで、各児童の特性に合わせて作られるのが障がい児用抱っこ紐です。障がい児用抱っこ紐の給付申請があった場合には、ぜひ前向きに検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか?
今後、当事者の意見やニーズの把握に努め、要件に該当するかを確認し、適宜、検討・見直しを図ってまいります。
妊産婦に対するタクシー利用料金助成について
2025年6月議会
提言)
産科誘致が実現していない本市において、市民の皆さんが安心して出産できる環境をつくるために、市内から距離のある産科へ直接向かう交通手段を提供することは大いに役に立つと思います。体調の急変でバスや電車の利用が困難、早朝や深夜はバス・電車が動かない、自家用車がないなどの状況に備えて、産科が開業するまでの間、タクシー利用料金を助成してはいかがでしょうか?
回答)
タクシー利用を含めた妊産婦の移動支援全体に対する助成として捉える必要があるものと考えており、現段階で全般的な助成の導入予定はございませんが、安心してこどもを産み育てられるよう、引き続き妊娠期から子育て期までの切れ目のない相談支援に努めてまいりたいと考えております。
産科誘致が実現していない本市において、市民の皆さんが安心して出産できる環境をつくるために、市内から距離のある産科へ直接向かう交通手段を提供することは大いに役に立つと思います。体調の急変でバスや電車の利用が困難、早朝や深夜はバス・電車が動かない、自家用車がないなどの状況に備えて、産科が開業するまでの間、タクシー利用料金を助成してはいかがでしょうか?
回答)
タクシー利用を含めた妊産婦の移動支援全体に対する助成として捉える必要があるものと考えており、現段階で全般的な助成の導入予定はございませんが、安心してこどもを産み育てられるよう、引き続き妊娠期から子育て期までの切れ目のない相談支援に努めてまいりたいと考えております。
子どもの建物からの転落事故防止対策について
2025年6月議会
提言)
消費者安全調査委員会で委員長を務める神戸大学中川教授は、「『窓の近くに足場を置かない』、『子どもを一人にしない』と繰り返し注意喚起しても事故は続発した。ソフト面の対策には限界がある」としています。
消費者安全調査委員会で委員長を務める神戸大学中川教授は、「『窓の近くに足場を置かない』、『子どもを一人にしない』と繰り返し注意喚起しても事故は続発した。ソフト面の対策には限界がある」としています。
ハード面からの転落防止対策については、補助錠、手すり、柵の設置等が有効とされ、国土交通省も「子育て支援型共同住宅推進事業」の中で、1戸当たり最大100万円の補助制度を用意しています。各マンションの管理組合を通すなどして、国土交通省の補助制度を案内してはと考えますが、いかがですか?
回答)
回答)
国の補助制度は、分譲、賃貸の区別なく、対象建物を共同住宅又は長屋に限定し、改修だけでなく新築も対象としております。このことから、周知の対象をマンションマンション管理組合に限定せず、市ホームページや広報において広く周知していきたいと考えています。
産後ドゥーラ(家事・育児等サポート)の利用補助について
2025年6月議会
提言)
産後ドゥーラは産前産後の女性をサポートする為に必要な知識・技術を体系的に学習しており、家事代行・ベビーシッターの役割も含め、特定の支援ではなく生活育児全般を包括的に支え、子育ての全てをサポートする存在として、母親と家族が安心できる環境を提供しています。産後の親御さん達の疲れた心と体をしっかりと休ませ、家族の幸せと生活の安定を保つためには、産後ドゥーラの利用補助が必要だと思いますが、いかがですか?
回答)
産後ドゥーラのほか民間のベビーシッターや家事ヘルパーサービスなどの情報をまとめ、妊娠届出時の面談等において、随時、情報提供を行っているところでございます。また、産後ドゥーラによる家事・育児等サービスに類似した事業といたしまして、「ホームスタート事業」、「産後ケア事業」等をを実施しております。「産後ケア事業」につきましては、事業の充実、利用の促進を図るための取り組みを実施しており、家庭ごとの状況に合わせ、こうした様々な支援を行っているところでございます。
提言)
産後ドゥーラは産前産後の女性をサポートする為に必要な知識・技術を体系的に学習しており、家事代行・ベビーシッターの役割も含め、特定の支援ではなく生活育児全般を包括的に支え、子育ての全てをサポートする存在として、母親と家族が安心できる環境を提供しています。産後の親御さん達の疲れた心と体をしっかりと休ませ、家族の幸せと生活の安定を保つためには、産後ドゥーラの利用補助が必要だと思いますが、いかがですか?
回答)
産後ドゥーラのほか民間のベビーシッターや家事ヘルパーサービスなどの情報をまとめ、妊娠届出時の面談等において、随時、情報提供を行っているところでございます。また、産後ドゥーラによる家事・育児等サービスに類似した事業といたしまして、「ホームスタート事業」、「産後ケア事業」等をを実施しております。「産後ケア事業」につきましては、事業の充実、利用の促進を図るための取り組みを実施しており、家庭ごとの状況に合わせ、こうした様々な支援を行っているところでございます。
子どもの将来の投票につながる親子連れ投票の推進
2025年3月議会
提言)
18歳未満の子どもは、大人と一緒であれば投票所に入ることができます。総務省は、子どもの頃に親の投票について行ったことのある人は、ない人に比べて投票参加率が20%以上高くなるとして、子どもと一緒に選挙に行くことを推奨しています。本市でも親子連れ投票を推進すべきでは?
回答)
親子連れ投票は、子どもが投票所の様子や親が投票する姿を見ることができ、家庭などで選挙や政治などについて話し合う機会になることから、国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していくための重要な主権者教育の一つであると認識しております。
このようなことから、親子連れ投票の推進を図ってまいりたいと考えております。
Vision
総務省は、主権者教育への取組として「親子連れ投票に係る周知チラシ」を作成し、選挙啓発に努めています。チラシの表面は親子で楽しめる「選挙の“まちがいさがし”」、裏面では親子連れ投票が将来の子どもの投票に繋がることを伝えています。
また、埼玉県をはじめ全国の多くの自治体がホームページで親子連れ投票を周知しています。
八潮市のホームページで親子連れ投票を周知すること、および総務省の「親子連れ投票に係る周知チラシ」を小中学校で保護者宛にメール配信することに関しては、本市としても前向きに対応するとの回答がありました。
親子連れ投票の推進は、将来的な八潮市の選挙投票率向上に必ずつながると考えます。
その後の進展)
八潮市ホームページに、新たに「親子連れ投票について」のページが設けられ、「選挙人の同伴する子ども(18歳未満)の投票所への入場について」、「親子連れ投票による効果」、「子どもと一緒に投票所へ入るときのルール」などが、総務省の「親子連れ投票に係る周知チラシ」とともにわかりやすく掲載されました。
提言)
18歳未満の子どもは、大人と一緒であれば投票所に入ることができます。総務省は、子どもの頃に親の投票について行ったことのある人は、ない人に比べて投票参加率が20%以上高くなるとして、子どもと一緒に選挙に行くことを推奨しています。本市でも親子連れ投票を推進すべきでは?
回答)
親子連れ投票は、子どもが投票所の様子や親が投票する姿を見ることができ、家庭などで選挙や政治などについて話し合う機会になることから、国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していくための重要な主権者教育の一つであると認識しております。
このようなことから、親子連れ投票の推進を図ってまいりたいと考えております。
Vision
総務省は、主権者教育への取組として「親子連れ投票に係る周知チラシ」を作成し、選挙啓発に努めています。チラシの表面は親子で楽しめる「選挙の“まちがいさがし”」、裏面では親子連れ投票が将来の子どもの投票に繋がることを伝えています。
また、埼玉県をはじめ全国の多くの自治体がホームページで親子連れ投票を周知しています。
八潮市のホームページで親子連れ投票を周知すること、および総務省の「親子連れ投票に係る周知チラシ」を小中学校で保護者宛にメール配信することに関しては、本市としても前向きに対応するとの回答がありました。
親子連れ投票の推進は、将来的な八潮市の選挙投票率向上に必ずつながると考えます。
その後の進展)
八潮市ホームページに、新たに「親子連れ投票について」のページが設けられ、「選挙人の同伴する子ども(18歳未満)の投票所への入場について」、「親子連れ投票による効果」、「子どもと一緒に投票所へ入るときのルール」などが、総務省の「親子連れ投票に係る周知チラシ」とともにわかりやすく掲載されました。
子どもの特徴を早期に発見し支援につなげる5歳児健診の実施
2025年3月議会
提言)
5歳は社会性が高まり、対人関係や発達の特徴が見えやすくなる時期であることから、こども家庭庁は発達障害などを早期に発見し必要な支援につなげるため、5歳児健診を実施する自治体に対し費用の補助を行うなどにより、全国の自治体での実施を目指しています。
本市でも5歳児健診を実施すべきと考えますが、検討状況は?
回答)
現在、こども家庭庁から示された「5歳児健康診査マニュアル」等を参考に、基礎的事項を確認するとともに、運営に関する課題等について整理しております。
具体的には、埼玉県主催の研修会に参加し、健診におけるフォローアップ体制の整備方法のほか、5歳児の発達の特徴や相談内容に即した保健指導の手法等について学び、職員間で情報を共有しております。また、5歳児健診を既に実施している和光市を視察し、本市における実施に向け、より良い運営方法等について検討を進めております。
提言)
5歳は社会性が高まり、対人関係や発達の特徴が見えやすくなる時期であることから、こども家庭庁は発達障害などを早期に発見し必要な支援につなげるため、5歳児健診を実施する自治体に対し費用の補助を行うなどにより、全国の自治体での実施を目指しています。
本市でも5歳児健診を実施すべきと考えますが、検討状況は?
回答)
現在、こども家庭庁から示された「5歳児健康診査マニュアル」等を参考に、基礎的事項を確認するとともに、運営に関する課題等について整理しております。
具体的には、埼玉県主催の研修会に参加し、健診におけるフォローアップ体制の整備方法のほか、5歳児の発達の特徴や相談内容に即した保健指導の手法等について学び、職員間で情報を共有しております。また、5歳児健診を既に実施している和光市を視察し、本市における実施に向け、より良い運営方法等について検討を進めております。
公設学童保育所の平日開所時間延長
2025年3月議会
提言)
現在、市内学童保育所の平日開所時間は、民間施設の午後7時30分までに対し、公設施設では1施設を除き午後6時30分までとなっています。また、利用できる学童保育所は小学校毎に決められているため、子どもの小学校入学に際し公設学童保育所を利用せざるを得ず、開所時間の影響で就労に困難をきたす保護者がいます。公設学童保育所の平日開所時間を午後7時30分まで延長べきでは?
回答)
働き方の多様化や、小学校ごとに通所できる学童保育所が決まっていることなどから、現在、開所時間の延長について検討を行っているところでございます。開所時間の延長に当たりましては、学童保育所における人材確保や、費用負担の在り方など、様々な課題があるものと考えておりますが、市といたしましては、引き続き開所時間の延長に向け、調査・検討を進めてまいりたいと考えております。
提言)
現在、市内学童保育所の平日開所時間は、民間施設の午後7時30分までに対し、公設施設では1施設を除き午後6時30分までとなっています。また、利用できる学童保育所は小学校毎に決められているため、子どもの小学校入学に際し公設学童保育所を利用せざるを得ず、開所時間の影響で就労に困難をきたす保護者がいます。公設学童保育所の平日開所時間を午後7時30分まで延長べきでは?
回答)
働き方の多様化や、小学校ごとに通所できる学童保育所が決まっていることなどから、現在、開所時間の延長について検討を行っているところでございます。開所時間の延長に当たりましては、学童保育所における人材確保や、費用負担の在り方など、様々な課題があるものと考えておりますが、市といたしましては、引き続き開所時間の延長に向け、調査・検討を進めてまいりたいと考えております。
市内中小企業者の経営力強化を後押しする施策
2024年12月議会
提言)
市内中小企業は、地域の活性化や雇用の確保に大きく貢献するなど、市民生活の向上と地域経済の発展に重要な役割を果たしています。
しかし、近年の原材料費高騰や人手不足などにより、中小企業を取り巻く経営環境は厳しくなっており、経営力の強化が求められています。
従業員の心身の健康状態を向上させる「健康経営」は、企業業績も向上させるとされています。市内中小企業において「健康経営」を推進すべきでは?
回答)
「健康経営」による従業員の健康保持・増進の取組が、結果的に業績や企業価値を向上さるとされております。
現在策定中である令和7年度を始期とする「第3次八潮市健康づくり行動計画」におきまして、「健康経営の実践」を新たな取組として設定することとしているところでございます。
市といたしましては、健康経営という考え方につきまして、市ホームページ等により広く普及啓発を図るとともに、関係部署とも連携し、健診受診率の向上やワークライフバランスの推進等、健康経営の実践を市内企業へ働きかけてまいりたいと考えております。
提言)
市内中小企業は、地域の活性化や雇用の確保に大きく貢献するなど、市民生活の向上と地域経済の発展に重要な役割を果たしています。
しかし、近年の原材料費高騰や人手不足などにより、中小企業を取り巻く経営環境は厳しくなっており、経営力の強化が求められています。
従業員の心身の健康状態を向上させる「健康経営」は、企業業績も向上させるとされています。市内中小企業において「健康経営」を推進すべきでは?
回答)
「健康経営」による従業員の健康保持・増進の取組が、結果的に業績や企業価値を向上さるとされております。
現在策定中である令和7年度を始期とする「第3次八潮市健康づくり行動計画」におきまして、「健康経営の実践」を新たな取組として設定することとしているところでございます。
市といたしましては、健康経営という考え方につきまして、市ホームページ等により広く普及啓発を図るとともに、関係部署とも連携し、健診受診率の向上やワークライフバランスの推進等、健康経営の実践を市内企業へ働きかけてまいりたいと考えております。
不登校児童生徒の健康診断受診に対する環境整備
2024年12月議会
提言)
小中学校での健康診断は、疾患等を早期に発見し治療につなげる重要な機会ですが、不登校の児童生徒にとって、学校での集団受診は非常に困難です。不登校で受診できず健康に深刻な影響が出た事例と対応の必要性が、新聞・テレビ等でも報じられています。
不登校の児童生徒に対して、検査・診察の時間や場所を工夫するなど、本市でも個別に配慮すべきでは?
回答)
不登校児童生徒に対し、個別に配慮することにつきまして、心臓健診は別会場で検査を実施しておりますが、その他の健診の会場は学校となっています。
不登校の児童生徒は、学校に行くことができない状況であったり、外出も難しい場合もございます。また、会場や医師のご都合等もあることから、対応につきましては、研究してまいりたいと考えております。
Vision
大阪府吹田市には、小中学生が学校外で健康診断を受ける際の費用を補助する仕組みがあります。
医師会の協力で、歯科以外の健診は学校医である内科の医療機関で受けられ、歯科も含めて、費用負担はありません。自分の学区の学校医でなくてもよく、7月から9月末の期間内であれば予約日時も自由。
昨年度は、これまで受診していなかった人の2割にあたる児童生徒が健康診断を受けたそうです。
不登校の児童生徒が、健康診断を受診できないことで、大人になって健康問題で苦しむことが無いよう、健康診断受診の環境整備に真摯に取り組むべきだと考えます。
提言)
小中学校での健康診断は、疾患等を早期に発見し治療につなげる重要な機会ですが、不登校の児童生徒にとって、学校での集団受診は非常に困難です。不登校で受診できず健康に深刻な影響が出た事例と対応の必要性が、新聞・テレビ等でも報じられています。
不登校の児童生徒に対して、検査・診察の時間や場所を工夫するなど、本市でも個別に配慮すべきでは?
回答)
不登校児童生徒に対し、個別に配慮することにつきまして、心臓健診は別会場で検査を実施しておりますが、その他の健診の会場は学校となっています。
不登校の児童生徒は、学校に行くことができない状況であったり、外出も難しい場合もございます。また、会場や医師のご都合等もあることから、対応につきましては、研究してまいりたいと考えております。
Vision
大阪府吹田市には、小中学生が学校外で健康診断を受ける際の費用を補助する仕組みがあります。
医師会の協力で、歯科以外の健診は学校医である内科の医療機関で受けられ、歯科も含めて、費用負担はありません。自分の学区の学校医でなくてもよく、7月から9月末の期間内であれば予約日時も自由。
昨年度は、これまで受診していなかった人の2割にあたる児童生徒が健康診断を受けたそうです。
不登校の児童生徒が、健康診断を受診できないことで、大人になって健康問題で苦しむことが無いよう、健康診断受診の環境整備に真摯に取り組むべきだと考えます。
災害発生時の在宅避難者及び車中泊避難者への支援
2024年12月議会
提言)
本年6月に修正された国の防災基本計画では、現実として避難所以外で避難生活を送る避難者が多くいること等を踏まえ、在宅避難者、車中泊避難者等への支援策を検討するよう自治体に求める記述が追加されましたが、本市の支援対策は?
回答)
令和6年6月に修正された国の防災基本計画では、「市町村は、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災 者支援に係る情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供するものとする。」また、「車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、在宅避難者と同様に、食料等の必要な物資や被災者支援に係る情報を提供する」との記述が追記されました。本市では、地域防災計画に、「避難所外避難者対策」の項目を設け、「在宅避難者や車中等に避難している避難者に係る情報の把握に努めるとともに、食料等必要な物資の配布、情報の提供等必要な支援を実施」することとしており、市内22か所の指定避難所におきまして、物資の配布等の支援を行うこととしております。ただ、在宅避難者の支援拠点あるいは車中泊避難の方の支援拠点、こういったものは、内閣府の在宅・車中泊避難者等の支援の手引を見ますと、行政がという記載がありますので、ここに関しては、今まで想定をしていないことが今回6月に記載されていますので、申し訳ございませんが、まだ詳細な検討までは至っておりません。今後検討させていただきたいと思います。
提言)
本年6月に修正された国の防災基本計画では、現実として避難所以外で避難生活を送る避難者が多くいること等を踏まえ、在宅避難者、車中泊避難者等への支援策を検討するよう自治体に求める記述が追加されましたが、本市の支援対策は?
回答)
令和6年6月に修正された国の防災基本計画では、「市町村は、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災 者支援に係る情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供するものとする。」また、「車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、在宅避難者と同様に、食料等の必要な物資や被災者支援に係る情報を提供する」との記述が追記されました。本市では、地域防災計画に、「避難所外避難者対策」の項目を設け、「在宅避難者や車中等に避難している避難者に係る情報の把握に努めるとともに、食料等必要な物資の配布、情報の提供等必要な支援を実施」することとしており、市内22か所の指定避難所におきまして、物資の配布等の支援を行うこととしております。ただ、在宅避難者の支援拠点あるいは車中泊避難の方の支援拠点、こういったものは、内閣府の在宅・車中泊避難者等の支援の手引を見ますと、行政がという記載がありますので、ここに関しては、今まで想定をしていないことが今回6月に記載されていますので、申し訳ございませんが、まだ詳細な検討までは至っておりません。今後検討させていただきたいと思います。
身寄りのない高齢者等の困りごとに対する支援
2024年9月議会
提言)
本市の高齢者単独世帯数については、2020年の国勢調査において3,531世帯と、2000年調査の692世帯に対し5.1倍となりました。今後、手助けできる近親者がいない一人暮らし高齢者の増加が想定されます。
このことに対応するため、「私と家族の安心ノート(エンディングノート)」に記載された情報等を本市へ登録していただき利用すべきでは?
回答)
市にエンディングノートのデータ等が残っていれば「もしも」の場合に円滑に物事が進むケースも考えられます。
終末期に対する不安を解消し、住み慣れた地域で安心して暮らしていただくための方策のひとつとして、他自治体の登録内容や開示の方法などを参考に調査・研究してまいりたいと考えております。
Vision
横須賀市では、全市民を対象にエンディングノートの保管場所を含め11項目の登録を受け付けていて、緊急時に医療機関や消防、警察、福祉事務所や親族等に対し必要に応じて情報を開示しており、登録者の増加に伴い医療機関や警察等からの問い合わせに応えられるケースが増えています。登録件数は、本年8月時点で約930件。
本市の人口は横須賀市の約4分の1ですから、同様に実施した場合、単純計算で約230件の登録が見込まれます。実施モデルがあり、結果も出ていて、ご本人、関係機関、そして本市、それぞれにとって円滑な対応を可能にし、手間と費用もさほど必要ありません。
身寄りのないご高齢者に寄り添い、毎日を安心して過ごしていただけるよう、できるだけ早い時期に事業を実施するべきだと考えます。
提言)
本市の高齢者単独世帯数については、2020年の国勢調査において3,531世帯と、2000年調査の692世帯に対し5.1倍となりました。今後、手助けできる近親者がいない一人暮らし高齢者の増加が想定されます。
このことに対応するため、「私と家族の安心ノート(エンディングノート)」に記載された情報等を本市へ登録していただき利用すべきでは?
回答)
市にエンディングノートのデータ等が残っていれば「もしも」の場合に円滑に物事が進むケースも考えられます。
終末期に対する不安を解消し、住み慣れた地域で安心して暮らしていただくための方策のひとつとして、他自治体の登録内容や開示の方法などを参考に調査・研究してまいりたいと考えております。
Vision
横須賀市では、全市民を対象にエンディングノートの保管場所を含め11項目の登録を受け付けていて、緊急時に医療機関や消防、警察、福祉事務所や親族等に対し必要に応じて情報を開示しており、登録者の増加に伴い医療機関や警察等からの問い合わせに応えられるケースが増えています。登録件数は、本年8月時点で約930件。
本市の人口は横須賀市の約4分の1ですから、同様に実施した場合、単純計算で約230件の登録が見込まれます。実施モデルがあり、結果も出ていて、ご本人、関係機関、そして本市、それぞれにとって円滑な対応を可能にし、手間と費用もさほど必要ありません。
身寄りのないご高齢者に寄り添い、毎日を安心して過ごしていただけるよう、できるだけ早い時期に事業を実施するべきだと考えます。
「八潮市こども計画」策定作業におけるこども・若者への意見聴取と反映
2024年9月議会
提言)
こども基本法第10条に基づき、本市では令和7年3月の「八潮市こども計画」策定に向け、現在、作業が進められています。こども・若者への意見聴取と計画への反映が重要だと考えますが、意見聴取と反映の状況は?
回答)
「就学前児童の保護者」や「小学生児童の保護者」を対象に実施したニーズ調査、また、子どもの保護者及び子ども・子育て支援に関する学識経験を有する者などで構成される子ども子育て支援審議会における意見聴取、さらには、第6次八潮市総合計画の策定に関して、小学生、中学生及び高校生に実施したアンケート調査でいただいた意見などを踏まえ、計画に位置付けする施策等を検討しているところでございます。さらに今後パブリックコメントの実施を予定しており、主にホームページで周知する予定ですが、こどもに対しては、小学校、中学校、図書館等に掲示する「キッズ広報やしお」などで広く周知することを予定しております。
その後の進展)
こどもからの意見を聴取するため「八潮市こども計画(やさしい版)」を小中学校に設置し、令和6年12月6日から32日間やしおキッズページより回答フォームにて意見を募集。21人のこどもが意見を提出し、子ども計画への反映が検討される。
提言)
こども基本法第10条に基づき、本市では令和7年3月の「八潮市こども計画」策定に向け、現在、作業が進められています。こども・若者への意見聴取と計画への反映が重要だと考えますが、意見聴取と反映の状況は?
回答)
「就学前児童の保護者」や「小学生児童の保護者」を対象に実施したニーズ調査、また、子どもの保護者及び子ども・子育て支援に関する学識経験を有する者などで構成される子ども子育て支援審議会における意見聴取、さらには、第6次八潮市総合計画の策定に関して、小学生、中学生及び高校生に実施したアンケート調査でいただいた意見などを踏まえ、計画に位置付けする施策等を検討しているところでございます。さらに今後パブリックコメントの実施を予定しており、主にホームページで周知する予定ですが、こどもに対しては、小学校、中学校、図書館等に掲示する「キッズ広報やしお」などで広く周知することを予定しております。
その後の進展)
こどもからの意見を聴取するため「八潮市こども計画(やさしい版)」を小中学校に設置し、令和6年12月6日から32日間やしおキッズページより回答フォームにて意見を募集。21人のこどもが意見を提出し、子ども計画への反映が検討される。
不登校長期化への対応
2024年6月議会
提言)
本市を含め全国的に不登校児童生徒数の増加傾向が続く状況を踏まえ、政府、埼玉県から新たな不登校対策が示されました。
本市でも児童生徒一人一人に応じた支援の一層の充実が必要であると考えます。不登校長期化への対応の状況は?
回答)
登校再開に向けた面談を行い、別室登校や時差登校など、無理のない登校方法を検討するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー及びさわやか相談員とも連携しながら、児童生徒一人一人に寄り添った対応を行っております。
Vision
提言)
本市を含め全国的に不登校児童生徒数の増加傾向が続く状況を踏まえ、政府、埼玉県から新たな不登校対策が示されました。
本市でも児童生徒一人一人に応じた支援の一層の充実が必要であると考えます。不登校長期化への対応の状況は?
回答)
登校再開に向けた面談を行い、別室登校や時差登校など、無理のない登校方法を検討するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー及びさわやか相談員とも連携しながら、児童生徒一人一人に寄り添った対応を行っております。
Vision
政府は、校内教育支援センター未設置校へ設置を促進し、落ち着いた空間で学習・生活できる環境を学校内に設けるとしています。これは大変重要なことで、本市でもスピード感をもって進める必要があります。
一方、学校に入れない児童生徒が学校以外で利用できる場所に関して、フリースクールや放課後デイサービスなどの各種情報を保護者に提供し、選択肢を広げることも必要です。
更に、自宅から出られない子どもにとって重要な役割を果たすのがオンラインによる支援です。1人1台端末を活用して自宅等から学べるようにするICTの環境整備と有効活用の体制づくりも急務です。
一方、学校に入れない児童生徒が学校以外で利用できる場所に関して、フリースクールや放課後デイサービスなどの各種情報を保護者に提供し、選択肢を広げることも必要です。
更に、自宅から出られない子どもにとって重要な役割を果たすのがオンラインによる支援です。1人1台端末を活用して自宅等から学べるようにするICTの環境整備と有効活用の体制づくりも急務です。
状況の異なる不登校児童生徒一人一人に寄り添った支援が、学びの保障、社会的自立、そして、子どもたちの素晴らしい未来へつながると考えます。
一人一人に寄り添った不登校児童生徒への支援
2024年6月議会
提言)
不登校児童生徒数の増加傾向が続く状況を踏まえ、政府及び埼玉県から新たな不登校対策が示されました。本市においても、これら対策への取組の徹底を初め、児童生徒一人一人の状況に応じた支援の一層の充実が必要かつ重要であると考えます。
不登校の早期発見と初期段階における対応状況は?
回答)
教員等が不登校の予兆をいち早く見つけ、迅速かつていねいな対応ができるよう、「不登校対策の手引き」を活用し、「不登校の予兆を見逃さないための視点」や「行動観察のポイント」「児童生徒が休みがちな時期や気にかけておきたい児童生徒の状況」「初期段階における対応」を、市内全小中学校で共通理解しております。
また本市では、毎月、長期欠席をしている児童生徒の把握を行っており、学校と教育委員会で連携しながら、不登校児童生徒の早期発見と早期対応に努めております。
提言)
不登校児童生徒数の増加傾向が続く状況を踏まえ、政府及び埼玉県から新たな不登校対策が示されました。本市においても、これら対策への取組の徹底を初め、児童生徒一人一人の状況に応じた支援の一層の充実が必要かつ重要であると考えます。
不登校の早期発見と初期段階における対応状況は?
回答)
教員等が不登校の予兆をいち早く見つけ、迅速かつていねいな対応ができるよう、「不登校対策の手引き」を活用し、「不登校の予兆を見逃さないための視点」や「行動観察のポイント」「児童生徒が休みがちな時期や気にかけておきたい児童生徒の状況」「初期段階における対応」を、市内全小中学校で共通理解しております。
また本市では、毎月、長期欠席をしている児童生徒の把握を行っており、学校と教育委員会で連携しながら、不登校児童生徒の早期発見と早期対応に努めております。
市役所新庁舎における安全・衛生管理活動
2024年3月議会
提言)
新庁舎の新たな環境における安全・衛生管理活動はご苦労も多いかと推察します。しかしながら、新庁舎における市民と職員の安全・健康を守るためには、今、集中して活動することが肝要であると考えますが、安全・衛生管理活動の実施状況は?
回答)
提言)
新庁舎の新たな環境における安全・衛生管理活動はご苦労も多いかと推察します。しかしながら、新庁舎における市民と職員の安全・健康を守るためには、今、集中して活動することが肝要であると考えますが、安全・衛生管理活動の実施状況は?
回答)
施設利用者に関する主な取組としましては、施設・設備に関する点検のほか、日常清掃、警備員の配置及びパトロールの実施、安全・快適な庁舎とするための案内板を設置するなどしております。
このほか、多目的室を活用した体操教室の開催や、栄養指導室を活用した保健指導など、健康を守る活動にも取り組むこととしております。
また、職員に関する主な取組としましては、健康診断の実施、執務室内の空気環境測定、健康管理に関する研修の実施や、産業医による職場巡視を行うこととしております。このほか、職員だけではなく施設利用者も対象とした避難訓練・消火訓練の実施に向け、検討しているところでございます。
耐震シェルター設置補助制度
2024年3月議会
提言)
地震で家屋が倒壊しても安全な生存空間を確保でき、改修に比べて安価で工期が短く賃貸住宅にも設置可能なことから、耐震シェルター、耐震ベッドに対する補助制度を設けるべきでは?
回答)
耐震シェルター、耐震ベッド設置に対する補助金の検討につきましては、近隣市町の交付制度の先進事例などを参考に、調査研究してまいります。
その後の進展)
令和7年度より、耐震シェルター、耐震ベッド設置費用の1/2、限度額20万円の補助制度が設けられました。
提言)
地震で家屋が倒壊しても安全な生存空間を確保でき、改修に比べて安価で工期が短く賃貸住宅にも設置可能なことから、耐震シェルター、耐震ベッドに対する補助制度を設けるべきでは?
回答)
耐震シェルター、耐震ベッド設置に対する補助金の検討につきましては、近隣市町の交付制度の先進事例などを参考に、調査研究してまいります。
その後の進展)
令和7年度より、耐震シェルター、耐震ベッド設置費用の1/2、限度額20万円の補助制度が設けられました。
災害に対する備えと周知
2024年3月議会
提言)
災害による被害を防ぐ或いは最小限に抑える、また、被災した際に心身の負担を可能な限り軽減するためには、日頃から災害に対して備えておくことが必要です。しかし、飲食料品やトイレ等に比べて注意が向きにくい備えもあります。その一つとして寒さへの備えが重要だと考えますが、寒さへの備えに対する配慮の状況は?
回答)
寒さへの備えとしましては、本市では令和6年2月末現在、毛布5,344枚、災害救助用カーペット1,989枚、寝袋602個、保温用アルミシート600枚、ハイブリットシート100枚を備蓄しております。
また、本市の指定避難所となる学校の体育館には、順次エアコンが設置される予定でございますが、停電になることも想定されることから、市民一人ひとりが自助として、防寒着、寝袋、保温用アルミシート、カイロ、カセットコンロ等を可能な範囲内で備えていただくよう、機会をとらえて周知・啓発に努めてまいります。
提言)
災害による被害を防ぐ或いは最小限に抑える、また、被災した際に心身の負担を可能な限り軽減するためには、日頃から災害に対して備えておくことが必要です。しかし、飲食料品やトイレ等に比べて注意が向きにくい備えもあります。その一つとして寒さへの備えが重要だと考えますが、寒さへの備えに対する配慮の状況は?
回答)
寒さへの備えとしましては、本市では令和6年2月末現在、毛布5,344枚、災害救助用カーペット1,989枚、寝袋602個、保温用アルミシート600枚、ハイブリットシート100枚を備蓄しております。
また、本市の指定避難所となる学校の体育館には、順次エアコンが設置される予定でございますが、停電になることも想定されることから、市民一人ひとりが自助として、防寒着、寝袋、保温用アルミシート、カイロ、カセットコンロ等を可能な範囲内で備えていただくよう、機会をとらえて周知・啓発に努めてまいります。
保育士支援制度に関する情報発信と保育士募集の広報
2024年3月議会
提言)
本市民間保育施設における保育士確保のため、市では保育士支援制度の拡充を図っています。
この施策を確実に保育士確保に結び付けるために、就職希望者に八潮市で働く魅力を紹介する冊子を作成し配布等するべきでは?
回答)
保育士確保に当たりましては、保育士支援制度等の周知が重要であると認識しております。保育士や保育士を目指す方一人ひとりの手に取って頂けるようなチラシや冊子の作成、配布などについて検討しているところでございます。
Vision
提言)
本市民間保育施設における保育士確保のため、市では保育士支援制度の拡充を図っています。
この施策を確実に保育士確保に結び付けるために、就職希望者に八潮市で働く魅力を紹介する冊子を作成し配布等するべきでは?
回答)
保育士確保に当たりましては、保育士支援制度等の周知が重要であると認識しております。保育士や保育士を目指す方一人ひとりの手に取って頂けるようなチラシや冊子の作成、配布などについて検討しているところでございます。
Vision
近隣市ホームページでは、県の事業なども含めた7~10程度の保育士支援制度の他、交通アクセスの良さ、市内ショッピングセンター、公園、イベント、先生や保護者の声、一日の仕事の様子なども紹介しています。
松戸市では冊子にもして、保育士養成学校の他、市の公共施設、ハローワーク、駅、ショッピングセンターなど様々な場所に配置しています。
松戸市では冊子にもして、保育士養成学校の他、市の公共施設、ハローワーク、駅、ショッピングセンターなど様々な場所に配置しています。
本市でも、保育士として働く魅力をより多く紹介し、冊子を作成し、様々な場所に配置して、ひとりでも多くの方に八潮で働く魅力が届くよう、積極的な情報発信と広報活動を行うことが重要です。
それが、本市全体としての保育士確保、保育環境と保育の質の維持・向上、そして、子ども達の笑顔につながるものと考えます。
その後の進展)
八潮市ホームページの「やしおでほいくしませんか?」ページにて、「民間保育施設ではたらく保育士を応援!八潮市の5つのサポート!」や「八潮市保育士奨学金返済支援事業補助金について」紹介、さらに、「保育士にインタビュー!」として、仕事のやりがい、職場の雰囲気、研修、休暇取得、働き方などについても紹介されるようになりました。
その後の進展)
八潮市ホームページの「やしおでほいくしませんか?」ページにて、「民間保育施設ではたらく保育士を応援!八潮市の5つのサポート!」や「八潮市保育士奨学金返済支援事業補助金について」紹介、さらに、「保育士にインタビュー!」として、仕事のやりがい、職場の雰囲気、研修、休暇取得、働き方などについても紹介されるようになりました。
八潮市土地開発公社の経費削減
2024年3月土地開発公社理事会
提言)
土地の購入や売払等の動きが少なく会計管理がシンプルになっているので、専用会計システムの契約を解除し、エクセルなどを利用し対応すれば良いのでは?
回答)
令和7年度より専用会計システムの利用を取りやめ、あわせてプリンターの賃借も取りやめて市所有の複合機を利用することとします。
その後の進展)
「八潮市土地開発公社 令和7年度予算」が賛成全員で可決され、専用会計システム及びプリンター利用料計13万円程度の歳出削減を実現しました。
提言)
土地の購入や売払等の動きが少なく会計管理がシンプルになっているので、専用会計システムの契約を解除し、エクセルなどを利用し対応すれば良いのでは?
回答)
令和7年度より専用会計システムの利用を取りやめ、あわせてプリンターの賃借も取りやめて市所有の複合機を利用することとします。
その後の進展)
「八潮市土地開発公社 令和7年度予算」が賛成全員で可決され、専用会計システム及びプリンター利用料計13万円程度の歳出削減を実現しました。
町会・自治会の防犯活動に対する支援・助成の拡充
2023年12月議会
提言)
地域の安全と安心な生活を守るため、各町会・自治会においては、夜間パトロール、防犯灯の電球切れ確認、児童帰宅時の声掛け運動、わんわんパトロール、ゴミの不法投棄或いは持ち去りに対するパトロール等の防犯活動を実施しています。しかしながら、会員の減少傾向もあり、防犯活動にも効率的・効果的な運営が求められています。防犯灯、防犯カメラ、犯罪抑止用看板設置等に対する助成の拡充すべきでは?
回答)
提言)
地域の安全と安心な生活を守るため、各町会・自治会においては、夜間パトロール、防犯灯の電球切れ確認、児童帰宅時の声掛け運動、わんわんパトロール、ゴミの不法投棄或いは持ち去りに対するパトロール等の防犯活動を実施しています。しかしながら、会員の減少傾向もあり、防犯活動にも効率的・効果的な運営が求められています。防犯灯、防犯カメラ、犯罪抑止用看板設置等に対する助成の拡充すべきでは?
回答)
防犯灯設置費の補助につきましては、1灯の設置に要した経費の3分の2以内で上限は6万円、LED灯の場合は上限が8万円。修繕費につきましては、1灯の修繕に要した経費の3分の2以内で上限が2万円、独立柱の撤去または建て替えは1か所につき上限20万円、また、電気代につきましては経費の全額を補助しております。 現在、新規に設置する防犯灯はLED灯であり、町会・自治会の負担はほとんどなく設置できている状況でございます。また、設置要望につきましても、各町会・自治会のご要望に応えられている状況でございます。
防犯カメラの助成につきましては、県内で防犯カメラの設置に対する補助を実施している自治体がございますので、先進自治体の取組事例を調査・研究してまいります。
また、犯罪抑止用看板につきましては、これまで町会・自治会の要望に応じてのぼり旗を配布しておりましたが、草加警察署からのぼり旗の管理に関して指摘を受けたことから、現在は配布を中止しております。今後につきましては、草加警察署と調整を行い、対応を検討してまいります。
その後の進展)
令和7年度より、継続的に撮影する録画機能付き防犯カメラを自宅敷地内に設置する市民に対し、設置費用の一部を補助金として交付する事業が実施されます。
民間事業者との災害協定締結促進と連携強化
2023年12月議会
提言)
地球温暖化の進行に伴う気候変動の影響で、台風・豪雨等の気象災害は激甚化・頻発化が目に見える形で進んでおります。また、今後発生が想定されている首都直下地震等の大規模地震への備えも怠ることはできません。
災害発生時に応急対策及び復旧活動を迅速、確実に進められるよう、民間事業者との連携を更に強化することが重要であると考えます。
民間事業者との災害協定締結を更に促進すべきでは?
回答)
災害時応援協定については、令和5年12月1日現在、45件の協定・覚書を民間事業者と締結しております。
今後は、災害対応の初動期、応急対応期、災害復旧・復興期など、フェーズ毎に求められる支援の洗い出しを行い、締結済み協定でカバーしきれない分野について、災害時応援協定締結を検討してまいります。
また、協定締結済みであっても、締結先が被災するリスクなどを考慮し、複数の事業者と災害時応援協定を締結することを進めてまいります。
提言)
地球温暖化の進行に伴う気候変動の影響で、台風・豪雨等の気象災害は激甚化・頻発化が目に見える形で進んでおります。また、今後発生が想定されている首都直下地震等の大規模地震への備えも怠ることはできません。
災害発生時に応急対策及び復旧活動を迅速、確実に進められるよう、民間事業者との連携を更に強化することが重要であると考えます。
民間事業者との災害協定締結を更に促進すべきでは?
回答)
災害時応援協定については、令和5年12月1日現在、45件の協定・覚書を民間事業者と締結しております。
今後は、災害対応の初動期、応急対応期、災害復旧・復興期など、フェーズ毎に求められる支援の洗い出しを行い、締結済み協定でカバーしきれない分野について、災害時応援協定締結を検討してまいります。
また、協定締結済みであっても、締結先が被災するリスクなどを考慮し、複数の事業者と災害時応援協定を締結することを進めてまいります。
一人暮らし高齢者に対する見守り活動体制の充実
2023年12月議会
提言)
本年7月に総務省から公表された「一人暮らしの高齢者に対する見守り活動に関する調査 結果報告書」では、我が国における高齢化の進行に伴い高齢者の単独世帯も増加しており、地域による見守り活動の重要性が増しているが、見守りの担い手に関する状況は厳しいものに変化し、見守り活動に更なる工夫が必要な状況が明らかになったと記しています。
民間事業者との連携を広げ、一人暮らし高齢者の見守り活動の体制を充実させるべきでは?
回答)
市では、支援を必要とする高齢者を速やかに把握し、福祉サービス等に繋げられるよう「高齢者支援ネットワーク」の体制を作っており、日頃から市内を巡回する事業者や、地域の商店、企業、医療機関、金融機関等177の事業所に、気にかかる高齢者を見かけた場合に市や地域包括センターに連絡するよう協力をお願いしています。
民間事業者との連携を広げ一人暮らし高齢者の見守り活動の体制を充実させることについては、「高齢者支援ネットワーク」の更なる登録事業所拡大に向け取り組むとともに、地域包括支援センターや、八潮市社会福祉協議会など他の見守り活動を行う事業者とも情報共有を図り、一人暮らし高齢者の見守り体制を充実させてまいります。
Vision
八潮市社会福祉協議会による「ひとり暮らし高齢者の見守り活動」では、民生委員、地域住民、乳酸菌飲料宅配事業者などが、見守りを必要とし登録しているひとり暮らし高齢者のお宅を定期的に訪問する、電話するなどして状況を確認しています。
この活動に郵便局、ガス事業者、新聞販売店、宅配事業者、金融機関、生協等の民間事業者にも参加してもらうことを提案。
日常業務の範囲中で、登録しているひとり暮らし高齢者のお宅の小さな異変、「新聞が何日もたまっている」、「同じ洗濯物が干したまま」、「雨戸が閉まったまま」「明かりがついたまま」などに気が付いた際に、市や社会福祉協議会に連絡をしてもらう協定を結び、見守り活動を支える民生委員が不足する中、民間事業者との連携を広げ、費用を掛けずに見守りの目を増やすことを要望しました。
提言)
本年7月に総務省から公表された「一人暮らしの高齢者に対する見守り活動に関する調査 結果報告書」では、我が国における高齢化の進行に伴い高齢者の単独世帯も増加しており、地域による見守り活動の重要性が増しているが、見守りの担い手に関する状況は厳しいものに変化し、見守り活動に更なる工夫が必要な状況が明らかになったと記しています。
民間事業者との連携を広げ、一人暮らし高齢者の見守り活動の体制を充実させるべきでは?
回答)
市では、支援を必要とする高齢者を速やかに把握し、福祉サービス等に繋げられるよう「高齢者支援ネットワーク」の体制を作っており、日頃から市内を巡回する事業者や、地域の商店、企業、医療機関、金融機関等177の事業所に、気にかかる高齢者を見かけた場合に市や地域包括センターに連絡するよう協力をお願いしています。
民間事業者との連携を広げ一人暮らし高齢者の見守り活動の体制を充実させることについては、「高齢者支援ネットワーク」の更なる登録事業所拡大に向け取り組むとともに、地域包括支援センターや、八潮市社会福祉協議会など他の見守り活動を行う事業者とも情報共有を図り、一人暮らし高齢者の見守り体制を充実させてまいります。
Vision
八潮市社会福祉協議会による「ひとり暮らし高齢者の見守り活動」では、民生委員、地域住民、乳酸菌飲料宅配事業者などが、見守りを必要とし登録しているひとり暮らし高齢者のお宅を定期的に訪問する、電話するなどして状況を確認しています。
この活動に郵便局、ガス事業者、新聞販売店、宅配事業者、金融機関、生協等の民間事業者にも参加してもらうことを提案。
日常業務の範囲中で、登録しているひとり暮らし高齢者のお宅の小さな異変、「新聞が何日もたまっている」、「同じ洗濯物が干したまま」、「雨戸が閉まったまま」「明かりがついたまま」などに気が付いた際に、市や社会福祉協議会に連絡をしてもらう協定を結び、見守り活動を支える民生委員が不足する中、民間事業者との連携を広げ、費用を掛けずに見守りの目を増やすことを要望しました。
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定への対応
2023年9月議会
提言)
厳しい暑さによる熱中症の対策を強化するため、改正気候変動適応法が本年4月28日に成立しました。本改正により、来年度から熱中症特別警戒情報が創設されます。
また、市町村長は冷房設備を有する公共施設や商業施設等を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定が可能となり、特別警戒情報の発表期間中、施設は一般に開放することが必要となります。
八潮市内全域に1か所でも多くのクーリングシェルターを開設するべく、民間施設にもクーリングシェルターとなってもらえるよう働きかけていく必要があると思いますが、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定に向けた準備状況は?
回答)
指定暑熱避難施設、クーリングシェルター指定に向けた準備状況についてでございますが、本年8月25日に県主催で開催されました気候変動適応法改正に伴う熱中症予防対策事業市町村説明会では、現在、環境省が設置した熱中症対策推進検討会において、熱中症特別警戒情報の運用に関する指針や、指定暑熱避難施設の指定・設置に関する手引などの検討がされている段階であり、詳細については確定しておらず、指針や手引の公開は年明けを予定しているとの説明でございました。
そのため、現時点では、引き続き熱中症対策に係る情報収集に努めるとともに、国・県からの具体的な方針が示された際には、本市における指定暑熱避難施設の在り方を検討してまいりたいと考えております。
その後の進展)
令和6年度より、市関連施設9か所がクーリングシェルターとして指定されています。
提言)
厳しい暑さによる熱中症の対策を強化するため、改正気候変動適応法が本年4月28日に成立しました。本改正により、来年度から熱中症特別警戒情報が創設されます。
また、市町村長は冷房設備を有する公共施設や商業施設等を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定が可能となり、特別警戒情報の発表期間中、施設は一般に開放することが必要となります。
八潮市内全域に1か所でも多くのクーリングシェルターを開設するべく、民間施設にもクーリングシェルターとなってもらえるよう働きかけていく必要があると思いますが、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定に向けた準備状況は?
回答)
指定暑熱避難施設、クーリングシェルター指定に向けた準備状況についてでございますが、本年8月25日に県主催で開催されました気候変動適応法改正に伴う熱中症予防対策事業市町村説明会では、現在、環境省が設置した熱中症対策推進検討会において、熱中症特別警戒情報の運用に関する指針や、指定暑熱避難施設の指定・設置に関する手引などの検討がされている段階であり、詳細については確定しておらず、指針や手引の公開は年明けを予定しているとの説明でございました。
そのため、現時点では、引き続き熱中症対策に係る情報収集に努めるとともに、国・県からの具体的な方針が示された際には、本市における指定暑熱避難施設の在り方を検討してまいりたいと考えております。
その後の進展)
令和6年度より、市関連施設9か所がクーリングシェルターとして指定されています。
災害時用トイレ準備に関する対応状況の確認
2023年9月議会
提言)
9月1日で関東大震災から100年。大災害に対する備えとしての災害時用携帯トイレの重要性に関し、市としての備蓄増量、市民への備蓄啓発について、昨年6月の定例会で一般質問を行いましたが、その後の状況は?
提言)
9月1日で関東大震災から100年。大災害に対する備えとしての災害時用携帯トイレの重要性に関し、市としての備蓄増量、市民への備蓄啓発について、昨年6月の定例会で一般質問を行いましたが、その後の状況は?
① 昨年6月時点と比較した本市の災害時用携帯トイレ備蓄量について
② 昨年6月以降に行った市民に対する災害時用携帯トイレ備蓄に関する啓発活動について
回答)
回答)
① 便座に袋をセットして使用後に凝固剤をふりかけるトイレセットを令和4年11月に5,000回分購入し、さらに、市内の事業者から2,500回分の寄付を頂いたため、昨年6月と比較して、7,500回分増の12,000回分となりました。
② 災害時用携帯トイレ備蓄に関する啓発活動につきましては、出前講座、子育て広場、こどもぼうさいまいすたーブラッシュアップ研修会、避難所開設訓練、やしお市民大学等で啓発するとともに、夜市において、防災PRの一環として、携帯トイレ備蓄に関しても説明をいたしました。
Vision② 災害時用携帯トイレ備蓄に関する啓発活動につきましては、出前講座、子育て広場、こどもぼうさいまいすたーブラッシュアップ研修会、避難所開設訓練、やしお市民大学等で啓発するとともに、夜市において、防災PRの一環として、携帯トイレ備蓄に関しても説明をいたしました。
八潮市としても、災害時用携帯トイレの重要性に鑑みて、たいへん力強く積極的に備蓄に関する施策を推進しています。
しかしながら、全市民分の災害時用トイレを八潮市として備蓄することは現実的でありません。そこで、重要になるのは各家庭における災害時用携帯トイレの備蓄ですが、水や食料に比べ家庭での備蓄率は低く約22%です。
地震、台風等による停電、断水、下水道の不通で水洗トイレが使えなくなると、排泄を我慢するために、水分や食品摂取を控えるようになり、健康被害と病状の悪化を招き死亡に至る災害関連死が増加します。
水洗トイレが使えなくなっても、排泄を我慢せず、必要な水分や食品をしっかり摂取することができるよう、みなさんのご家庭でも、「1日の平均トイレ利用回数5~7回×家族人数×7日分」の災害時用携帯トイレを備蓄しましょう!
気候不安(エコ不安)対策
2023年9月議会
提言)
気候変動による環境破壊に対して恐れを抱く気候不安。眠れない、涙が溢れる、怒りを覚える等の症状が現れることもあり、WHOもメンタルヘルスへの深刻な影響を問題視しています。
電通総研の調査では、日本のZ世代の73%が気候変動による「不安」を感じ、49%が「私の日常生活にネガティブな影響を与えている」と回答するなど、日本でも気候不安の広がりが確認されました。
本市としても気候不安に対応すべきと考えますが、今後検討すべき対策は?
回答)
現時点では、基本的には精神的な不安等を抱える方への対応と同様と考えております。市では、「心の健康講座」を開催し、知識の普及啓発を図るとともに、個別の相談に関しては、心の健康相談や保健師による相談を行い、受診が必要な場合は受診勧奨を行い、不安の軽減に努めています。
今後も、これら事業を継続するとともに、気候不安について新たな知見があった際には、適宜、対応してまいりたいと存じます。
Vision
2021年に英国バース大学の研究者が中心となり10か国で実施した調査「子どもと若者における気候不安と気候変動への政府の対応についての考え方」では、対象者の約3分の2が気候変動について「非常にまたは極度に心配」し、84%が少なくとも多少は心配していることが明らかになりました。また、半数以上が「悲しみ、不安、怒り、無力感、罪悪感を抱いている」と回答しました。
これから先、気候不安に陥る子どもや若者が出てきた時に、安心させ、不安をポジティブなエネルギーに転換させることができるよう、しっかりと準備を進めることが重要です。
提言)
気候変動による環境破壊に対して恐れを抱く気候不安。眠れない、涙が溢れる、怒りを覚える等の症状が現れることもあり、WHOもメンタルヘルスへの深刻な影響を問題視しています。
電通総研の調査では、日本のZ世代の73%が気候変動による「不安」を感じ、49%が「私の日常生活にネガティブな影響を与えている」と回答するなど、日本でも気候不安の広がりが確認されました。
本市としても気候不安に対応すべきと考えますが、今後検討すべき対策は?
回答)
現時点では、基本的には精神的な不安等を抱える方への対応と同様と考えております。市では、「心の健康講座」を開催し、知識の普及啓発を図るとともに、個別の相談に関しては、心の健康相談や保健師による相談を行い、受診が必要な場合は受診勧奨を行い、不安の軽減に努めています。
今後も、これら事業を継続するとともに、気候不安について新たな知見があった際には、適宜、対応してまいりたいと存じます。
Vision
2021年に英国バース大学の研究者が中心となり10か国で実施した調査「子どもと若者における気候不安と気候変動への政府の対応についての考え方」では、対象者の約3分の2が気候変動について「非常にまたは極度に心配」し、84%が少なくとも多少は心配していることが明らかになりました。また、半数以上が「悲しみ、不安、怒り、無力感、罪悪感を抱いている」と回答しました。
これから先、気候不安に陥る子どもや若者が出てきた時に、安心させ、不安をポジティブなエネルギーに転換させることができるよう、しっかりと準備を進めることが重要です。
子どもたちの安全を守る学校事故防止対策
2023年6月議会
提言)
報道番組NHKスペシャルでは、日本スポーツ振興センターが公開している2005~2021年度までの学校事故デーベース、死亡事故と障害が残った事故の合わせて8729件を分析。見えてきたのは、「何度も同じような事故を繰り返す」実態で、本市にとっても大変示唆に富む内容でした。
子どもたちの安全を守る万全な学校事故防止対策が必要だと考えますが、本市の対策の状況は?
回答)
学校事故防止対策については、国や県の通知に基づき、市や各学校において様々な対策を講じております。県や市では各学校を訪問して、危険個所等の施設設備の管理を徹底し、各学校では、「ヒヤリハット」いわゆる危ないことが起こったが幸い災害には至らなかった事象の事例について共有し、大きな事故に繋がらないよう未然防止対策を講じております。また、安全委員として選任された生徒が、自分たちの活動している場所を見て回り、安全点検を行う取り組みなども実施しております。
Vision
「熱中症」「窓からの転落」「ゴールポスト転倒」「プールでの事故」「給食中の窒息」等の学校事故8729件。その一つ一つの事故の向こうで、多くの子どもたちの未来が失われていました。
学校事故で障害を負った当事者の方は、「自分と同じような目に遭ってほしくない。安全が確保された中で伸び伸び過ごしてほしい、安全な場所をつくってもらいたい。」と話していました。
全ての子どもたちの安全と未来を守り、キラキラと豊かに伸びやかに成長できるよう、安全管理の専門家等にも参加を求めるなど、八潮市内の小中学校においても学校事故防止対策に万全を期する必要があると考えます。
提言)
報道番組NHKスペシャルでは、日本スポーツ振興センターが公開している2005~2021年度までの学校事故デーベース、死亡事故と障害が残った事故の合わせて8729件を分析。見えてきたのは、「何度も同じような事故を繰り返す」実態で、本市にとっても大変示唆に富む内容でした。
子どもたちの安全を守る万全な学校事故防止対策が必要だと考えますが、本市の対策の状況は?
回答)
学校事故防止対策については、国や県の通知に基づき、市や各学校において様々な対策を講じております。県や市では各学校を訪問して、危険個所等の施設設備の管理を徹底し、各学校では、「ヒヤリハット」いわゆる危ないことが起こったが幸い災害には至らなかった事象の事例について共有し、大きな事故に繋がらないよう未然防止対策を講じております。また、安全委員として選任された生徒が、自分たちの活動している場所を見て回り、安全点検を行う取り組みなども実施しております。
Vision
「熱中症」「窓からの転落」「ゴールポスト転倒」「プールでの事故」「給食中の窒息」等の学校事故8729件。その一つ一つの事故の向こうで、多くの子どもたちの未来が失われていました。
学校事故で障害を負った当事者の方は、「自分と同じような目に遭ってほしくない。安全が確保された中で伸び伸び過ごしてほしい、安全な場所をつくってもらいたい。」と話していました。
全ての子どもたちの安全と未来を守り、キラキラと豊かに伸びやかに成長できるよう、安全管理の専門家等にも参加を求めるなど、八潮市内の小中学校においても学校事故防止対策に万全を期する必要があると考えます。
SNS等での「闇バイト」募集から子どもたちを守る対策
2023年6月議会
提言)
警視庁が本年3月24日に公表した特殊詐欺の実行役らと「闇バイト」を巡る分析結果では、SNS等を通して中学生をも「闇バイト」に引き込んでいる実態が明らかにされました。
本市としても、子供がSNS上における「闇バイト」情報等をきっかけに加害者となる危険性を、保護者等に対し注意喚起すべきでは?
回答)
県教育委員会が提供する「埼玉県ネットトラブル注意報」「お子さまスマートフォンだいじょうぶ?」等を活用しております。「埼玉県ネットトラブル注意報」令和5年3月8日付第12号は「インターネット上の『闇バイト』募集に注意を!」でした。本号では、「闇バイト」の手口をはじめ、簡単に抜け出せなくなり、加害者になる過程が説明されており、「あやしい募集には絶対応募してはいけません」と注意喚起されています。
各小中学校において、各種たよりや学級懇談会等でこれら内容を各家庭・保護者等に周知し、注意喚起を促しております。
提言)
警視庁が本年3月24日に公表した特殊詐欺の実行役らと「闇バイト」を巡る分析結果では、SNS等を通して中学生をも「闇バイト」に引き込んでいる実態が明らかにされました。
本市としても、子供がSNS上における「闇バイト」情報等をきっかけに加害者となる危険性を、保護者等に対し注意喚起すべきでは?
回答)
県教育委員会が提供する「埼玉県ネットトラブル注意報」「お子さまスマートフォンだいじょうぶ?」等を活用しております。「埼玉県ネットトラブル注意報」令和5年3月8日付第12号は「インターネット上の『闇バイト』募集に注意を!」でした。本号では、「闇バイト」の手口をはじめ、簡単に抜け出せなくなり、加害者になる過程が説明されており、「あやしい募集には絶対応募してはいけません」と注意喚起されています。
各小中学校において、各種たよりや学級懇談会等でこれら内容を各家庭・保護者等に周知し、注意喚起を促しております。
地域一体となった小学校登下校の見守り活動
2023年3月議会
提言)
長時間労働が、心身の健康や教育の質等に与える影響が危惧され、教員の皆さんの働き方改革が進められています。
一方、共働き世帯が増加する中、保護者の方からは、見守り活動について多くの声が寄せられています。
子供達の安全と安心を守るために、地域が一体となった見守り活動に繋げるべく、地域ボランティアと連携した取り組みをすべきでは?
回答)
教職員の働き方改革を推進する観点から、各校におきましては、児童生徒の登校時間を遅らせる検討が進んでおります。
一方で、登校時間が遅くなることで、保護者の方が、旗振り後の通勤に支障が生ずるため、旗振り活動に参加することが難しくなるとの声も聞いております。
今後の旗振り活動の在り方については、交通指導員の増員、ボランティアによる対応、地域の方々の協力なども視野に入れながら、PTA、学校、地域、教育委員会が連携し、より良い方策を見出すことで、児童生徒の安全な登下校を推進してまいりたいと考えております。
Vision
交通指導員さんは人員確保難が続き、保護者もだんだん見守り活動への参加が難しくなり、登下校の見守り活動の担い手が減少する中、活動維持のため保護者が費用を負担し外部委託する学校、活動廃止を検討する学校なども出てきています。
関係者が連携できる場と機会を設けて地域連携を進め、ボランティアさんにも定期的に見守り当番に参加してもらうなど、地域一体で小学校登下校を見守り、地域のみんなが一緒に子ども達の健やかな成長を見守っていける体制づくりが必要だと考えます。
提言)
長時間労働が、心身の健康や教育の質等に与える影響が危惧され、教員の皆さんの働き方改革が進められています。
一方、共働き世帯が増加する中、保護者の方からは、見守り活動について多くの声が寄せられています。
子供達の安全と安心を守るために、地域が一体となった見守り活動に繋げるべく、地域ボランティアと連携した取り組みをすべきでは?
回答)
教職員の働き方改革を推進する観点から、各校におきましては、児童生徒の登校時間を遅らせる検討が進んでおります。
一方で、登校時間が遅くなることで、保護者の方が、旗振り後の通勤に支障が生ずるため、旗振り活動に参加することが難しくなるとの声も聞いております。
今後の旗振り活動の在り方については、交通指導員の増員、ボランティアによる対応、地域の方々の協力なども視野に入れながら、PTA、学校、地域、教育委員会が連携し、より良い方策を見出すことで、児童生徒の安全な登下校を推進してまいりたいと考えております。
Vision
交通指導員さんは人員確保難が続き、保護者もだんだん見守り活動への参加が難しくなり、登下校の見守り活動の担い手が減少する中、活動維持のため保護者が費用を負担し外部委託する学校、活動廃止を検討する学校なども出てきています。
関係者が連携できる場と機会を設けて地域連携を進め、ボランティアさんにも定期的に見守り当番に参加してもらうなど、地域一体で小学校登下校を見守り、地域のみんなが一緒に子ども達の健やかな成長を見守っていける体制づくりが必要だと考えます。
子育てを全力で応援する保育サービスの充実
2023年3月議会
提言)
① 市内保育園への「おむつサブスク」「おひるね用コット」導入推進について
保護者、保育士さん共に、負担が軽減され、保育の質の向上にも繋がります。ぜひ、導入を推進しては?
② 保育事故・不適切保育の未然防止対策について
a.園児を逆さ吊りする等した横浜市での不適切保育、行政指導が行われたのは、同僚保育士が最初に園へ報告してから、なんと1年4か月後です。未然防止対策が重要ですが、本市おける各保育施設に対する確認、対応の体制は?
b.八潮市では保育士に対し月額2千円の補助だが、近隣市が月額4万円以上の補助を行う中、保育士を確保し保育の質を向上させるため、月額4万5千円程度へ補助増額しては?
回答)
① メリット、デメリット等、導入自治体の状況について調査研究してまいります。
② a.市では、民間保育施設からの相談に応じて適宜助言等を行うことや、指導監査等において保育内容を監査するなどして、保育事故・不適切保育の未然防止に努めており、今後におきましても、民間保育施設と連携・協力し、児童が安全で安心して生活できる保育の提供に努めてまいります。
b.保育士に対する補助増額については、近隣自治体の状況等を調査し検討してまいります。
その後の進展)
2024年1月から、保育士経験年数により月額3万円~5万円への補助増額が実施され、子ども達のための質の高い安定した保育環境の提供が前進。
提言)
① 市内保育園への「おむつサブスク」「おひるね用コット」導入推進について
保護者、保育士さん共に、負担が軽減され、保育の質の向上にも繋がります。ぜひ、導入を推進しては?
② 保育事故・不適切保育の未然防止対策について
a.園児を逆さ吊りする等した横浜市での不適切保育、行政指導が行われたのは、同僚保育士が最初に園へ報告してから、なんと1年4か月後です。未然防止対策が重要ですが、本市おける各保育施設に対する確認、対応の体制は?
b.八潮市では保育士に対し月額2千円の補助だが、近隣市が月額4万円以上の補助を行う中、保育士を確保し保育の質を向上させるため、月額4万5千円程度へ補助増額しては?
回答)
① メリット、デメリット等、導入自治体の状況について調査研究してまいります。
② a.市では、民間保育施設からの相談に応じて適宜助言等を行うことや、指導監査等において保育内容を監査するなどして、保育事故・不適切保育の未然防止に努めており、今後におきましても、民間保育施設と連携・協力し、児童が安全で安心して生活できる保育の提供に努めてまいります。
b.保育士に対する補助増額については、近隣自治体の状況等を調査し検討してまいります。
その後の進展)
2024年1月から、保育士経験年数により月額3万円~5万円への補助増額が実施され、子ども達のための質の高い安定した保育環境の提供が前進。
健康経営の推進
2022年12月議会
提言)
人口減少、少子高齢化が進展する中、将来的な労働人口減少に対応する人的生産性の向上が重要な課題となっており、健康管理を経営的視点から考え戦略的に実践し、健康増進で、従業員の活力向上、生産性の向上、医療費の削減等につなげる「健康経営」を推進する動きが広がっています。
特に日経平均株価を構成する225銘柄では8割を超える企業が認定の前提となる健康経営度調査に回答するなど必須の経営戦略となりつつあります。
健康経営を推進すべきでは?
回答)
「健康経営」を推進することにより、業績向上や企業価値の向上が期待されております。自治体においても「健康経営」に取り組むことで、職員が心身を良好な状態に保ち、意欲的に働くことができる環境が醸成されることにより組織が活性化し、それをもって質の高い市民サービスの提供につながることが期待されています。
このようなことから、経済産業省が制度設計を行った「健康経営優良法人」の認定を受けることにつきまして、既に認定を受けている自治体の取り組み事例等を参考に調査・研究してまいりたいと考えております。
その後の進展)
令和7年度を始期とする「第3次八潮市健康づくり行動計画」において、「健康経営の実践」が新たな取り組みとして設定されました。
提言)
人口減少、少子高齢化が進展する中、将来的な労働人口減少に対応する人的生産性の向上が重要な課題となっており、健康管理を経営的視点から考え戦略的に実践し、健康増進で、従業員の活力向上、生産性の向上、医療費の削減等につなげる「健康経営」を推進する動きが広がっています。
特に日経平均株価を構成する225銘柄では8割を超える企業が認定の前提となる健康経営度調査に回答するなど必須の経営戦略となりつつあります。
健康経営を推進すべきでは?
回答)
「健康経営」を推進することにより、業績向上や企業価値の向上が期待されております。自治体においても「健康経営」に取り組むことで、職員が心身を良好な状態に保ち、意欲的に働くことができる環境が醸成されることにより組織が活性化し、それをもって質の高い市民サービスの提供につながることが期待されています。
このようなことから、経済産業省が制度設計を行った「健康経営優良法人」の認定を受けることにつきまして、既に認定を受けている自治体の取り組み事例等を参考に調査・研究してまいりたいと考えております。
その後の進展)
令和7年度を始期とする「第3次八潮市健康づくり行動計画」において、「健康経営の実践」が新たな取り組みとして設定されました。
(仮称)外環八潮パーキングエリアが防災拠点として果たす役割と活用
2022年9月議会
提言)
令和3年3月に、広域災害応急対策の拠点となる防災機能を有する「道の駅」や高速道路のサービスエリア・パーキングエリアの自動車駐車場について、国土交通大臣が「防災拠点自動車駐車場」として指定する制度が創設されました。
ぜひ、防災拠点として活用すべきと考えますが、外環自動車道に整備が計画されている(仮称)外環八潮パーキングエリアの防災拠点としての役割と活用について本市の考えは?
回答)
(仮称)外環八潮パーキングエリアが「防災拠点自動車駐車場」に指定されますと、本市にとりましては、災害時の有効な防災拠点の一つになるものと考えております。
「防災拠点自動車駐車場」として指定されるためには、国土交通大臣と自動車駐車場の道路管理者である東日本高速道路株式会社との間で、協議を行い、同意が必要となっておりますことから、庁内関係部署と連携を図りながら、機会を捉えて東日本高速道路株式会社に対し要望を行うとともに、八潮市地域防災計画への位置づけについても検討してまいります。
Vision
東日本高速道路株式会社は、大規模災害時に防災拠点として活用することを考慮したSA・PAの整備として、最大規模のSA・PAでは、自家発電設備、防災倉庫、給水設備、井戸、ヘリポート等の整備やガソリン貯蔵量の増量などが行われています。
(仮称)外環八潮パーキングエリアを八潮市の防災拠点として活用するために、計画段階から東日本高速道路株式会社、消防、警察、自衛隊、医療機関等の関係各所と緊密な連携を図っていくことが重要だと考えます。
提言)
令和3年3月に、広域災害応急対策の拠点となる防災機能を有する「道の駅」や高速道路のサービスエリア・パーキングエリアの自動車駐車場について、国土交通大臣が「防災拠点自動車駐車場」として指定する制度が創設されました。
ぜひ、防災拠点として活用すべきと考えますが、外環自動車道に整備が計画されている(仮称)外環八潮パーキングエリアの防災拠点としての役割と活用について本市の考えは?
回答)
(仮称)外環八潮パーキングエリアが「防災拠点自動車駐車場」に指定されますと、本市にとりましては、災害時の有効な防災拠点の一つになるものと考えております。
「防災拠点自動車駐車場」として指定されるためには、国土交通大臣と自動車駐車場の道路管理者である東日本高速道路株式会社との間で、協議を行い、同意が必要となっておりますことから、庁内関係部署と連携を図りながら、機会を捉えて東日本高速道路株式会社に対し要望を行うとともに、八潮市地域防災計画への位置づけについても検討してまいります。
Vision
東日本高速道路株式会社は、大規模災害時に防災拠点として活用することを考慮したSA・PAの整備として、最大規模のSA・PAでは、自家発電設備、防災倉庫、給水設備、井戸、ヘリポート等の整備やガソリン貯蔵量の増量などが行われています。
(仮称)外環八潮パーキングエリアを八潮市の防災拠点として活用するために、計画段階から東日本高速道路株式会社、消防、警察、自衛隊、医療機関等の関係各所と緊密な連携を図っていくことが重要だと考えます。
(仮称)外環八潮パーキングエリアを活用した八潮市の魅力発信と観光・産業振興
2022年9月議会
提言)
(仮称)外環八潮パーキングエリア(PA)の計画駐車台数は、常磐自動車道上り線守谷サービスエリア等とも肩を並べ、八潮市の魅力発信にとって大きなチャンスであると考えます。
外環八潮PAを活用した八潮市の魅力発信と観光・産業振興を行うべきだと考えますが、本市の考えは?
回答)
外環八潮PAは、観光・産業振興はもとより、本市の魅力発信にとって大きなチャンスであると考えております。
外環八潮PA内商業施設で販売する商品を市内事業者で共同開発することについては、八潮市の特産品などを取り扱っていただく可能性があるものと考えており、本市の産業振興はもとより八潮市の魅力を発信する観点から、「個性的かつ魅力的」な商品を開発することは有効な手段の一つであると考えております。
今後、東日本高速道路株式会社との協議はもとより庁内関係部局や八潮市商工会など関係団体との連携のもと、市内事業者により共同開発に繋がる取組について調査・研究を行う等、必要な取り組みを進めてまいりたいと考えております。
その後の進展)
外環八潮PAの近くスマートインターチェンジを降りた場所に、八潮市として「道の駅やしお」整備が計画されたため、PAと道の駅の事業の棲み分けなど、東日本高速道路株式会社と協議が行われています。
提言)
(仮称)外環八潮パーキングエリア(PA)の計画駐車台数は、常磐自動車道上り線守谷サービスエリア等とも肩を並べ、八潮市の魅力発信にとって大きなチャンスであると考えます。
外環八潮PAを活用した八潮市の魅力発信と観光・産業振興を行うべきだと考えますが、本市の考えは?
回答)
外環八潮PAは、観光・産業振興はもとより、本市の魅力発信にとって大きなチャンスであると考えております。
外環八潮PA内商業施設で販売する商品を市内事業者で共同開発することについては、八潮市の特産品などを取り扱っていただく可能性があるものと考えており、本市の産業振興はもとより八潮市の魅力を発信する観点から、「個性的かつ魅力的」な商品を開発することは有効な手段の一つであると考えております。
今後、東日本高速道路株式会社との協議はもとより庁内関係部局や八潮市商工会など関係団体との連携のもと、市内事業者により共同開発に繋がる取組について調査・研究を行う等、必要な取り組みを進めてまいりたいと考えております。
その後の進展)
外環八潮PAの近くスマートインターチェンジを降りた場所に、八潮市として「道の駅やしお」整備が計画されたため、PAと道の駅の事業の棲み分けなど、東日本高速道路株式会社と協議が行われています。
市道0680号線における実効性ある交通安全対策
2022年6月議会
提言)
浮塚・大曽根地区を通る市道0680号線(八潮三郷東西線西端やおきんさん前の交差点から首都高速迄の区間)は、利用する歩行者・自転車にとって大変危険な状況であり、車両通行は地域住民の極めて大きな犠牲の上に成り立っています。
市道0680号線における短期間で実現可能な交通安全対策と、地域住民も参加した交通安全対策協議会の開催が必要だと考えますが、市としての考えは?
回答)
短期間で実現可能な交通安全対策といたしましては、消えかかった路面表示の復旧のほか、注意喚起の看板や電柱幕の設置、見通しの悪い交差点への道路反射鏡や道路照明灯の設置、交差点の中心に自発光式道路鋲の設置、路面標示が浮き上がって見えるイメージハンプなどが考えられます。
交通安全対策に関する協議会に関しましては、地域にお住まいの方や、周辺の事業所の方の意見を踏まえる必要がございます。まずは、地域の方々のご意見を丁寧に伺いながら、警察や庁内関係部署と協議し、更なる交通安全対策について検討してまいりたいと存じます。
Vision
短期間で実現可能な交通安全対策のほかに長期的観点からの道路網整備まで、地住民域の皆様もそれぞれに様々な考えをお持ちです。
市道0680号線における実効性ある交通安全対策を実現するためには、地域住民、八潮市、警察、埼玉県が緊密に連携・協力しながら進める「地域住民参加の交通安全対策協議会」の場で意見、情報、アイディアを交換し、より良い解決策を導き出していく事が大変重要です。
みんなの力を合わせて安全で安心して通行できる市道0680号線を実現してまいります。
その後の進展)
2023年7月に、地域住民、八潮市職員、草加警察署員が参加して「交通安全対策に関する意見交換会」が開催され、意見に基づき安全対策が進められています。
提言)
浮塚・大曽根地区を通る市道0680号線(八潮三郷東西線西端やおきんさん前の交差点から首都高速迄の区間)は、利用する歩行者・自転車にとって大変危険な状況であり、車両通行は地域住民の極めて大きな犠牲の上に成り立っています。
市道0680号線における短期間で実現可能な交通安全対策と、地域住民も参加した交通安全対策協議会の開催が必要だと考えますが、市としての考えは?
回答)
短期間で実現可能な交通安全対策といたしましては、消えかかった路面表示の復旧のほか、注意喚起の看板や電柱幕の設置、見通しの悪い交差点への道路反射鏡や道路照明灯の設置、交差点の中心に自発光式道路鋲の設置、路面標示が浮き上がって見えるイメージハンプなどが考えられます。
交通安全対策に関する協議会に関しましては、地域にお住まいの方や、周辺の事業所の方の意見を踏まえる必要がございます。まずは、地域の方々のご意見を丁寧に伺いながら、警察や庁内関係部署と協議し、更なる交通安全対策について検討してまいりたいと存じます。
Vision
短期間で実現可能な交通安全対策のほかに長期的観点からの道路網整備まで、地住民域の皆様もそれぞれに様々な考えをお持ちです。
市道0680号線における実効性ある交通安全対策を実現するためには、地域住民、八潮市、警察、埼玉県が緊密に連携・協力しながら進める「地域住民参加の交通安全対策協議会」の場で意見、情報、アイディアを交換し、より良い解決策を導き出していく事が大変重要です。
みんなの力を合わせて安全で安心して通行できる市道0680号線を実現してまいります。
その後の進展)
2023年7月に、地域住民、八潮市職員、草加警察署員が参加して「交通安全対策に関する意見交換会」が開催され、意見に基づき安全対策が進められています。
本市指定緊急避難場所、指定避難所における災害時用トイレの準備
2022年6月議会
提言)
避難所等における災害時用トイレの利用については、阪神淡路大震災、東日本大震災等でも大変過酷な現実があったことが報告されています。
災害時用トイレの準備が万全でないと、避難者の方にとって不衛生・不快な状況となり、ただでさえ困難な避難所生活を一層困難なものにします。
災害時用トイレにおける女性・子供・高齢者・障がい者等への配慮が必要ですが、配慮の状況は?
回答)
災害時用トイレにおける女性・子供・高齢者・障がい者等への配慮は、大変重要であると認識しているところでございます。
今後、避難所で使用されるトイレの洋式化、増設及び多目的トイレの新設など様々なニーズを取り入れるよう働きかけてまいりたいと考えております。
また、仮設トイレを設置する場合は、女性用と男性用の割合を3対1とすることを目標とし、その他にも設置場所や防犯対策、トイレまでの導線における段差の解消など様々なニーズに配慮してまいりたいと考えております。
提言)
避難所等における災害時用トイレの利用については、阪神淡路大震災、東日本大震災等でも大変過酷な現実があったことが報告されています。
災害時用トイレの準備が万全でないと、避難者の方にとって不衛生・不快な状況となり、ただでさえ困難な避難所生活を一層困難なものにします。
災害時用トイレにおける女性・子供・高齢者・障がい者等への配慮が必要ですが、配慮の状況は?
回答)
災害時用トイレにおける女性・子供・高齢者・障がい者等への配慮は、大変重要であると認識しているところでございます。
今後、避難所で使用されるトイレの洋式化、増設及び多目的トイレの新設など様々なニーズを取り入れるよう働きかけてまいりたいと考えております。
また、仮設トイレを設置する場合は、女性用と男性用の割合を3対1とすることを目標とし、その他にも設置場所や防犯対策、トイレまでの導線における段差の解消など様々なニーズに配慮してまいりたいと考えております。
コミュニティバスの運行管理状況に対する本市としての確認体制
2022年3月議会
提言)
提言)
令和3年6月に千葉県八街市で小学生が死傷する大変痛ましい交通事故が発生したことを受け、令和4年4月より、安全運転管理者の選任事業所に対し運転前の点呼・アルコールチェックを義務化する改正道路交通法施行規則が順次施行されます。
八潮市コミュニティバスにおいても管理強化が必要ですが、運行管理状況に対する本市としての確認体制は?
回答)
コニュニティバスは、本市との協定に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた東武バスセントラルが運行しており、八潮営業所全体では運転手が56人、運行管理者が6人、アルコール検知器が1台(予備に1台あり)とのことです。
その中で、八潮市コニュニティバスにつきましては、1日3台のバスを3人の運転手で運行しており、旅客自動車運送事業規則に従い厳しい安全管理のもとで運行されております。具体的には、乗務員は、乗車前にアルコール検知器を使用してアルコールチェックを行い、運行管理者が問題ないことを確認してから当日の運行ダイヤ表と鍵を渡し、乗務が終わった後にも同様のチェックを行っているとのことです。
本市としましても、機会を捉え安全管理の徹底を働きかけてまいりたいと存じます。
Vision
八潮市政で第一に優先されるものとして、人命に勝るものは無いと思います。
市民から愛称とラッピングデザインを募集して完成した「ハッピーこまちゃん号」です。本年4月1日の道路交通法施行規則改正を機に、再度、安全意識を新たにして、運行事業者と連携しての徹底した運行管理と安全管理により、無事故で安全な運行を市民の皆さんに示して頂きたいと思います。
コニュニティバスは、本市との協定に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた東武バスセントラルが運行しており、八潮営業所全体では運転手が56人、運行管理者が6人、アルコール検知器が1台(予備に1台あり)とのことです。
その中で、八潮市コニュニティバスにつきましては、1日3台のバスを3人の運転手で運行しており、旅客自動車運送事業規則に従い厳しい安全管理のもとで運行されております。具体的には、乗務員は、乗車前にアルコール検知器を使用してアルコールチェックを行い、運行管理者が問題ないことを確認してから当日の運行ダイヤ表と鍵を渡し、乗務が終わった後にも同様のチェックを行っているとのことです。
本市としましても、機会を捉え安全管理の徹底を働きかけてまいりたいと存じます。
Vision
八潮市政で第一に優先されるものとして、人命に勝るものは無いと思います。
市民から愛称とラッピングデザインを募集して完成した「ハッピーこまちゃん号」です。本年4月1日の道路交通法施行規則改正を機に、再度、安全意識を新たにして、運行事業者と連携しての徹底した運行管理と安全管理により、無事故で安全な運行を市民の皆さんに示して頂きたいと思います。
公用車等の運行管理
2022年3月議会
提言)
令和3年6月に千葉県八街市で飲酒運転により小学生が死傷する大変痛ましい交通事故が発生したことを受け、同年8月に関係閣僚会議で「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」が決定されました。
これを踏まえ、令和4年4月より、安全運転管理者の選任事業所に対し運転前の点呼・アルコールチェックを義務化する改正道路交通法施行規則が順次施行されます。管理を強化すべきと考えますが、本年4月1日以降の公用車運行管理体制と管理内容は?
回答)
ご質問のとおり、本年4月1日より、運転前後におきまして、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で酒気帯びの有無を確認する事及び、同年10月1日からはアルコール検知器を使用した酒気帯びの確認が義務化されました。
本市におきましても、本年4月1日より、運転者の酒気帯びの有無を確認することとし、具体的な運用方法について、最終的な調整を行っている段階でございます。
その後の進展)
運転前後に、アルコール検知器を使用した酒気帯びの確認が実施されており、安全に運行するための管理が行われています。
提言)
令和3年6月に千葉県八街市で飲酒運転により小学生が死傷する大変痛ましい交通事故が発生したことを受け、同年8月に関係閣僚会議で「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」が決定されました。
これを踏まえ、令和4年4月より、安全運転管理者の選任事業所に対し運転前の点呼・アルコールチェックを義務化する改正道路交通法施行規則が順次施行されます。管理を強化すべきと考えますが、本年4月1日以降の公用車運行管理体制と管理内容は?
回答)
ご質問のとおり、本年4月1日より、運転前後におきまして、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で酒気帯びの有無を確認する事及び、同年10月1日からはアルコール検知器を使用した酒気帯びの確認が義務化されました。
本市におきましても、本年4月1日より、運転者の酒気帯びの有無を確認することとし、具体的な運用方法について、最終的な調整を行っている段階でございます。
その後の進展)
運転前後に、アルコール検知器を使用した酒気帯びの確認が実施されており、安全に運行するための管理が行われています。
RPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)とAI-OCRの活用推進
2021年12月議会
提言)
RPAは、パソコンで行っている定型事務作業を自動化できるソフトウェアロボットで、マウス操作やキーボード入力手順などを記憶し、画面上をカーソルが自動で動き作業を行います。メリットは、人的ミスを防ぐ、スピ―ディ、24時間稼働可能、コストの大幅削減などが挙げられます。
AI-OCRは、人工知能を利用したOCR(光学的文字認識技術)で、識字率が格段に高くなっています。
RPAとAI-OCRは、既に多くの自治体や企業で導入されており、業務効率化、生産性向上を実現しています。足立区でも実証実験が行われ、6業務において、年間で合計約1,400時間の削減、費用対効果は年間で約415万円になるという結果が出ました。
推進すべきだと考えますが、本市におけるRPAとAI-OCRの活用推進の具体的計画は?
回答)
現在、今後の導入に向け、各所属における手続き申請書等の運用状況について調査し取りまとめを行っているところです。
本市におきましても、RPAとAI-OCRの導入にあたりましては、足立区や他自治体の事例等も参考にしながら、実証実験事業の導入も視野に入れ、業務の効率化や費用対効果を十分に検証し、取り組んでまいりたいと考えております。
提言)
RPAは、パソコンで行っている定型事務作業を自動化できるソフトウェアロボットで、マウス操作やキーボード入力手順などを記憶し、画面上をカーソルが自動で動き作業を行います。メリットは、人的ミスを防ぐ、スピ―ディ、24時間稼働可能、コストの大幅削減などが挙げられます。
AI-OCRは、人工知能を利用したOCR(光学的文字認識技術)で、識字率が格段に高くなっています。
RPAとAI-OCRは、既に多くの自治体や企業で導入されており、業務効率化、生産性向上を実現しています。足立区でも実証実験が行われ、6業務において、年間で合計約1,400時間の削減、費用対効果は年間で約415万円になるという結果が出ました。
推進すべきだと考えますが、本市におけるRPAとAI-OCRの活用推進の具体的計画は?
回答)
現在、今後の導入に向け、各所属における手続き申請書等の運用状況について調査し取りまとめを行っているところです。
本市におきましても、RPAとAI-OCRの導入にあたりましては、足立区や他自治体の事例等も参考にしながら、実証実験事業の導入も視野に入れ、業務の効率化や費用対効果を十分に検証し、取り組んでまいりたいと考えております。
Vision
八潮市においても、2025年から人口は減少に転じ、2035年に高齢化率が25%を超えることが予測されています。
RPAとAI-OCRの活用により業務の効率化・生産性向上・経費削減を図り、生み出された人的資源と財源を子ども・高齢者・障がい者などぬくもりを必要とする方々に活用し、最高の住民満足を実現させていくことがとても大切になると考えます。
その後の進展)
様々な業務においてRPAとAI-OCRの導入が進められており、効率化と生産性向上が図られています。
八潮市においても、2025年から人口は減少に転じ、2035年に高齢化率が25%を超えることが予測されています。
RPAとAI-OCRの活用により業務の効率化・生産性向上・経費削減を図り、生み出された人的資源と財源を子ども・高齢者・障がい者などぬくもりを必要とする方々に活用し、最高の住民満足を実現させていくことがとても大切になると考えます。
その後の進展)
様々な業務においてRPAとAI-OCRの導入が進められており、効率化と生産性向上が図られています。
DX(デジタルト・ランスフォ ーメーション)の推進
2021年12月議会
提言)
DX(デジタルト・ランスフォーメーション)は、ITの浸透で、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させていくものです。
急速な少子高齢化の進展、生産年齢人口(15歳から64歳)の減少が招く労働力不足、社会保障制度の給付と負担のバランスの崩壊、経済規模の縮小、財政危機、国際競争力の低下など、様々な社会的・経済的な課題の深刻化が強く懸念されます。
DXの推進により、業務の効率化、省力・省人化、生産性向上、経費削減を図り、生み出された財源と人的資源を子ども・高齢者・障がい者などぬくもりを必要とする方々に活用し、少ない人員、少ない支出で最高の住民満足を実現させるべきでは?
回答)
総務省では、本年7月に「自治体DX推進手順書」を発出し、DXの取り組みを総合的かつ効果的に推進する上で、市としての全体的な方針や計画を策定することが有用であるとされておりますことから、本市におきましても、方針や計画の策定に向け、取り組んでまいります。
その後の進展)
2024年1月の新庁舎開庁に合わせ、書かない窓口、セミセルフレジが導入されるなど、DXへの具体的取り組みが進行中で住民満足の向上が図られています。
提言)
DX(デジタルト・ランスフォーメーション)は、ITの浸透で、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させていくものです。
急速な少子高齢化の進展、生産年齢人口(15歳から64歳)の減少が招く労働力不足、社会保障制度の給付と負担のバランスの崩壊、経済規模の縮小、財政危機、国際競争力の低下など、様々な社会的・経済的な課題の深刻化が強く懸念されます。
DXの推進により、業務の効率化、省力・省人化、生産性向上、経費削減を図り、生み出された財源と人的資源を子ども・高齢者・障がい者などぬくもりを必要とする方々に活用し、少ない人員、少ない支出で最高の住民満足を実現させるべきでは?
回答)
総務省では、本年7月に「自治体DX推進手順書」を発出し、DXの取り組みを総合的かつ効果的に推進する上で、市としての全体的な方針や計画を策定することが有用であるとされておりますことから、本市におきましても、方針や計画の策定に向け、取り組んでまいります。
その後の進展)
2024年1月の新庁舎開庁に合わせ、書かない窓口、セミセルフレジが導入されるなど、DXへの具体的取り組みが進行中で住民満足の向上が図られています。